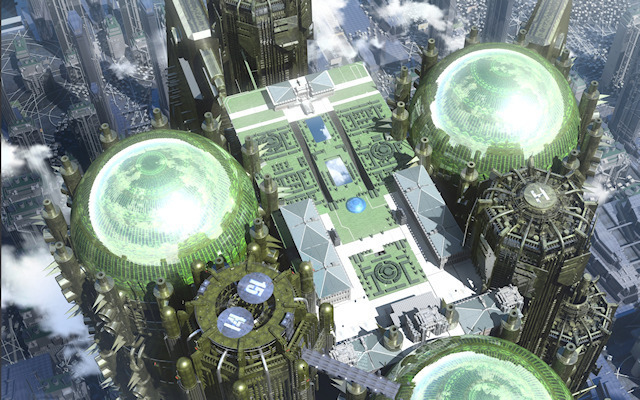自己同一性(アイデンティティ)は記憶と結びついている。私が私であるという同一性を確認できるのは、記憶があるからだ。もし私が記憶喪失になれば、もはや私にとって「私」とは何か、を決定することは不可能になる。私とは、私の記憶そのものだ。だが、人の記憶は曖昧なものだ。その曖昧性は、私たちのアイデンティティを万華鏡のごとく錯覚させる。
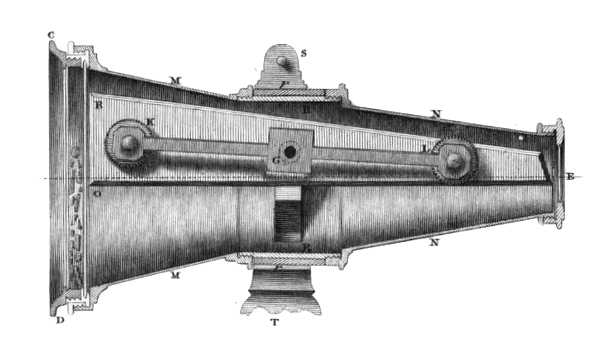
─ 「ソクラテス」を訂正することは可能か?
日本語、原宿、結城夏嶺・・・同類の中でほかとは違う固有の意味や定義を持つ名前・固有名。こうした固有名を聞いて、あなたは何をイメージするだろうか。愛すべき母国語か、思い出の地か、二度と会いたくない人か──それぞれのイメージは人によって異なるだろう。それは、固有名が一般名よりもさらに人の記憶と深く結びついたものだからだ。それは、固有名を定義づけることの難しさからも分かる。
たとえば、「ソクラテス」という固有名をどう定義づければよいだろうか。辞書に書いてある定義をそのまま使えばよいだろうか。あるいは、「男である」や「哲学者である」といった要素を無数に並べていけば、最終的にはその定義を確定できるだろうか。答えは否。私たちのほとんどは、辞書に書かれている「ソクラテス」の定義をすべて知っている訳ではない。あるいは人によっては、辞書の定義よりも多くのことを知っている場合もあるだろう。私たちは、辞書通りに言葉を使うわけではないのだ。
また、「ソクラテス」に当てはまる定義を無数に並べていっても、その定義そのものが訂正されてしまう可能性すらある。「ソクラテスは実は女だった」や、「ソクラテスは哲学者ではなかった」といった命題は、論理的には成立する。もしそれらが成立してしまった場合、私たちは「ソクラテス」という固有名ではなく、その定義の方を訂正する。そして、相変わらず「ソクラテス」という固有名を使い続ける。そうして「ソクラテス」の名のもとに、新たな人物イメージが生み出される。
私たちは固有名というものを定義からではなく、その名前にまつわる記憶から意味を確定させている。だから辞書とはズレた使い方であっても、その名前がどのように使われてきたかという記憶から、人々は意味を確定することができる。またその固有名に関する新たな歴史(記憶)が “発見” されれば、その定義を訂正することもあるのだ。
記憶との結びつきが強い固有名は、一般名よりもこうした “雑な” 使い方が許されることが多い。なぜなら前回説明したように、私たちの記憶は曖昧で、その都度訂正されるようなものだからだ。ゆえに固有名は、さまざまな人の解釈の幅にも耐えられるものとなる。これはまさしく、共同体のアイデンティティの本質である。
共同体のアイデンティティは定義によって決まるのではなく、我々の記憶(歴史)が決めるものだ。記憶との結びつきが強い固有名が、ほかとの差異=境界を作り出すために共同体のアイデンティティとして選ばれ、訂正され続ける。もちろん、一般名だって我々の記憶と無関係なものではないし、固有名と同様の性質を持っていることもある。しかし、こと共同体のアイデンティティとしては、一般名と比べて記憶の “濃度” が高く、曖昧化されやすい固有名の方が、よりふさわしいといえるだろう。
□ ◆ □
─ 「わたし」と「我々」を結えるもの
曖昧な共同体のアイデンティティとしての固有名は、これまたルールが曖昧な「言語ゲーム」によって持続していくことが可能になる。3.11で発生した原発事故後の福島復興を取材した「リスクと生きる、死者と生きる」(石戸諭)には、このことを示唆する箇所がある。
「末続に住む人たちは、みな自分たちの米が一番美味しいと言う。遠藤さんは遠藤さんの米が一番だと言い、別の家は自分たちこそが一番なのだと主張する。他の地域からやってくる人たちには、とりあえず「末続で取れた米」がうまいという。たぶん、それが文化と呼ばれるものなのだろう」
『リスクと生きる、死者と生きる』, 石戸諭
この一節は、共同体のアイデンティティと固有名との関係をよく表している。単なる「米」という一般名ではなく、「遠藤さんの米」という小さな固有名が「末続の米」というより大きな固有名に吸収され、その地域共同体のアイデンティティが生み出される。それぞれの家の人たちは、自分の家の米を指すものとして「〇〇の米」とならんで「末続の米」という固有名を使うだろう。このように言葉の意味にズレがあってもコミュニケーションは成立する。それは、私たちのコミュニケーションがルールが曖昧な「言語ゲーム」だからだ。
やがて共同体のメンバーが「死」によって入れ替わり、「末続の米」という固有名(アイデンティティ)が曖昧になっていくことで、その定義は新たな世代が作った米によってアップデートされていく。「末続の米」という伝統= “タテのつながり” は、複数の糸が撚り合わさったものとして形作られていく。曖昧な言語ゲームは、いつまでも「遠藤さんの米」をその糸の一本として矛盾なく「末続の米」につなぎ留めつづける。こうして結果的に、遠藤さんの子孫たちも、他者が作った「末続の米」にさえ、自分たちのアイデンティティを錯覚できるようになる。これが文化を生む共同体の「循環運動」だ。
▷ ▼ ◁
─ 訂正されつづけるタイムライン
私たちの「言語ゲーム」も「記憶」も曖昧だからこそ、言葉と記憶とが互いに訂正し合う循環運動が生まれる。死者によって紡がれてきた曖昧な “タテのつながり” が、私たちの言語ゲーム=ヨコのつながりの審判・観客となる。言語ゲームはルールが曖昧だから、これまた曖昧な言葉の意味のズレを審判・観客からの “視線” を借りながら調整しつつ、コミュニケーションを成立させる。そうして日常の「生活の流れ」ができると、人々の記憶が新たに訂正されていき、”現在の視点” ができあがる。そして、そこからふたたび “タテのつながり” が形成・訂正されていく。すべてが曖昧だからこそ、タテ・ヨコのつながりが矛盾なくダイナミックな一体になる。この構造がアイデンティティを錯覚させる。
共同体における「固有名」は、この訂正の循環運動というダイナミズムを体現しているのだ。これらの循環運動の中には、客観的なものなど何もない。すべてが曖昧だから起きる錯覚によって成り立っている。これこそ、「錯覚」が共同体の本質たる所以だ。
◯ ● ◯
─ 不明の差出人に気づくとき
ここまで「固有名の訂正可能性」を通じて共同体のメカニズムを見てきた。固有名は、私たちの記憶が曖昧になっていくからこそ、訂正可能だ。しかし、記憶が強まるからこそ固有名が訂正されるケースもある。その鍵を握るのが、「贈与」だ。
「贈与」というのは複雑な行為だ。贈り物を受け取った人はふつう、それに対してお返しをしようとする。しかし、それでは贈与にならず、Give & Take の「交換」になってしまう。では、そもそも贈与とはどうすれば可能になるのか。
この問題をクリアするためには、贈与は差出人不明である必要がある。贈与する時に、受取人に気づかれてはいけないのだ。「鶴の恩返し」で機織りをしているのが鶴だと知られてはいけないように。そうしてはじめて、一方的な “Give” である贈与が可能になる。しかしその贈与が、いつか気づかれる瞬間がある。受取人が、「あれは贈与だったのか」と過去を振り返って思う時、何が起きるのだろうか。SF作家ケン・リュウの「紙の動物園」を参考に見ていこう。
主人公のジャックは、父親がアメリカ人、母親が中国人のハーフであり、コネチカット州に住んでいる。ジャックの母親は、折り紙でつくった動物に命を吹き込むことができた。生き生きと動き出し、鳴き声をあげる折り紙の動物たち。その中でもとくに、「老虎(ラオフー)」と呼ばれる虎の折り紙が、ジャックのお気に入りだった。だがジャックは、アメリカ文化の中で成長していくにつれ、英語もろくにできず、アメリカでの生活に馴染めない母親のことを毛嫌いするようになる。彼は鏡を覗きこみながら「ぼくはどこも母さんに似ていない、どこも」と思うようになった。同時に、母親が作り出した紙の動物たちもゴミのように感じられ、箱に入れて屋根裏部屋に押し込めてしまう。その後も、ジャックと母親のギクシャクした関係は続き、折り紙の動物が作られることもなくなった。そして、母親は癌で若くして亡くなってしまう。
しばらくしたある日、屋根裏部屋に押し込んでいた老虎がジャックのもとにやって来る。ボロボロになっていた老虎は、ジャックの膝の上でひとりでに折り目をほどいて広がっていき、一通の手紙となった。そこには生前、母親が息子に向けて書いた中国語の文字が所狭しと書きつけられていた。彼はすぐに、中国語が分かる人に手紙を読み上げてもらう。そこには、母が中国の文化大革命の混乱が原因でアメリカに渡ってきたこと、苦しい環境で生まれた息子がどれだけ愛おしかったかということ、そしてそんな愛する息子からまともに相手にしてもらえなくなって胸が張り裂けそうなほど辛かったことについて書かれていた。母は、自分に似た面影のある息子の顔を見て、居場所を見つけていたのだ。
ジャックはその手紙を読み聞かされたとき、「手紙の言葉が体に染み込んでくるのを感じた」。その時、彼は母からの「贈与」に気づいたのだろう。彼は、母の手紙に書かれた「愛」という漢字を何度も何度もなぞり書きした。自分と母を似せようとするかのように。
差出人不明の贈与は、後になって気づかれる。差出人は未来へ贈与を渡し、受取人は過去から贈与を受け取る。モノクロだった過去の記憶は、贈与を受けることによって鮮烈に生まれ変わり、現在の私たちにノスタルジーのような強い感情を湧き起こす。「似てない」と毛嫌いしていた母親との思い出(記憶)が訂正され、「似ている」という錯覚さえ起こしてしまう。過去の記憶が、現在の自分に寄り添ってその意味を訂正するからだ。それは自分だけの意味(定義)、つまり固有名性を持つようになったということだ。こうして現在と過去のタテの時間軸がつながる。
これが、贈与による「固有名化」である。その力は、対象のもともとの固有名性を強めるだけでなく、一般名を固有名にすることさえ可能だ。たとえば、なんの変哲もない、大量生産された「時計」でも、そこに過去の大事な思い出が付与されれば、唯一無二の、自分だけの固有名としての「時計」として生まれ変わるだろう。このように、過去の記憶を訂正して呼び起こす贈与には、あらゆる物事を固有名化してしまう可能性がある。これは人間が “感情” によって世界を解釈する生き物だからこそ起こり得ることだ。
■ □ ■
─ あまりに物語的な
人間は、自分の人生を物語(ストーリー)で理解しようとする生き物だ。そのため、常に何かしらの形で、身の回りのものごとに原因と結果を見出そうとする。たとえば、スポーツ選手が大会で優勝した時、「努力すれば必ず報われると証明された」と言うことがあるが、これは端的に言って間違っている。その選手がいくら努力したと言っても、他にもっと努力した選手がいたかもしれない。その成功には、本人の努力以外の要素が多分に含まれている。そこには、コントロール不可能な偶然性もある。だから、こうした発言がなされる度に、反発が起きる。しかし、本人にとっては努力と優勝は原因と結果であり、もはや必然性のあるストーリーとなっている。これは知性の問題ではない。人が「わかった!」と真理を確信するのは、正解が決まっているペーパーテストの答え合わせをするような行為とは異なる。そうではなく、矛盾していたりバラバラになっていた知識や経験が急に結びつき、新たなストーリーとなった時に「ああ、そうだったのか!」と「真理」を確信=錯覚する。この時に湧き上がる大きな感情が、我々にある種の思考停止をもたらすことにより、疑いようのない確信が得られるのだ。文筆家・千野帽子が「物語は人生を救うのか」で言い当てたように、「わかる」と思う気持ちは感情以外のなにものでもない。
◇ ■ ◇
─ 過去は「わたし」から逆算された
過去からの贈与は、私たちの感情を激しく揺さぶる。私たちの「現在」と過去とを結びつける「ストーリー」ができあがり、疑いようのない「真理」を確信=錯覚させるからだ。その時、過去の記憶は、現在の私たちを “説明” するように訂正され、自分だけの固有名をつくる。嫌だった思い出が、かけがえのない素敵な思い出になり、なんてことのない記憶がトラウマとなる。そうした時に、人は本当の意味で変えられてしまったり、変わろうと切望する。
「民族という虚構」で小坂井敏晶は次のように説明する。
我々人間は常に変化する。変化自体が問題なのではない。強制的に変化させられる、あるいは逆に、変化したい方向に変化できない事態が問題なのである。苦しんだ末に宗教の道に入る人を思い浮かべよう。この人にとっては入信つまり信仰上の変化を遂げることで自己同一性を維持できるのであり、もし入信を禁止され、もとのままの状態を余儀なくされるなら、かえって自己同一性の危機を生み出す。ここでは変化が同一性を救い、無変化が同一性を破壊している。改宗または棄教という自己の変化自体からは何ら問題は発生しない。なりたいものになれないと感ずる時、また、なりたくないものにならなければならないと感ずる時に同一性の危機は訪れる。
『民族という虚構』, 小坂井敏晶
「私」という固有名は、常に変化しており、普段、人はそのことについて無自覚だ。しかし、「本当の自分」というものを強く意識=錯覚する瞬間がある。それは、過去の記憶からの贈与によってもたらされる。その時、人は大きな感情に揺さぶられ、「これしかない!」と、そこに自己同一性(アイデンティティ)を錯覚する。我々の “現在” は、過去の記憶から照射された「虚構」なのかもしれない。
ところで、前々回紹介したメイヘムというバンドのリーダーであった「ユーロニモス」という青年を覚えているだろうか。実は、この名前はステージネームであり、本名ではない。彼の本名は、「オイスタイン・オーシェト」という。彼の過激なパフォーマンスは、「ユーロニモス」という固有名を作り出し、その固有名にアイデンティティを見出したことが悲劇を招いてしまった。そんな彼が、「オイスタイン・オーシェト」という固有名をアイデンティティとして回復するためには、何が必要だったのか。そのヒントは、やはり記憶をめぐる「贈与」にあるだろう。
To Be Continued.
Next discussion hopefully to be posted someday.