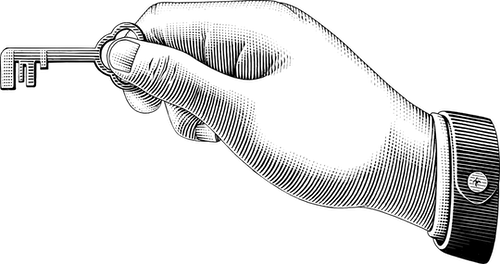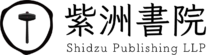夏の沼津。私はとある作品の「聖地巡礼」でその街に来ていた。初めて来た場所にも関わらず、どこか懐かしさや親しみを感じる。夏の日差しを反射する、というよりはそれ自体が発光しているかのような炭酸の海。星々を呑みこむ紫煙の夜空。そして何より、星空を予感させる間接照明のような夕焼けの砂浜。
どれも初めて見る景色───いや、その景色は確かに、そこに「再現」されていた。そこで私はノスタルジーのような親しみや懐かしさを覚えたのだ。まるで「帰ってきた」かのようなこの感覚に、私の気分は高揚していた。
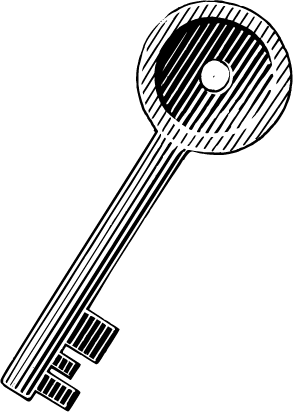
─ 観光客が感じるノスタルジーとは
自分の出自とは無縁なはずの場に、ノスタルジーを感じてしまう。この奇妙な現象は、バルバラ・カッサンの『ノスタルジー 〜我が家にいるとはどういうことか〜』という本のテーマになっている。カッサンはパリ生まれの哲学者で、仕事も子育てもパリでしている。だから、ふつうに考えればパリにノスタルジーを感じるものだと思われるが、彼女は別荘のあるコルシカにノスタルジーを感じると告白している。(コルシカに対する思い入れや、現地の人たちに迎え入れられた体験が、ノスタルジーを感じさせるのではないか、と彼女は推測している)
さまざまな栄誉ある賞を手にした哲学エリートの彼女は、オデュッセウス、アエネアス、アーレントといった様々な古典を題材にノスタルジーをめぐる考察をここで展開している。しかし、この本の中で一際、私の目を引いたのは、「開かれたノスタルジー」 “Sehnsucht” という語だった。これもまた一見、奇妙な用語ではないか。
ノスタルジーというのは、そもそも「閉じた」もののはずだ。それは、自分だけの思い出に浸ったり、仲間と共通の思い出語りに耽ったりするような、外部を寄せ付けない閉鎖性のあるものである。だから、ノスタルジーが「開かれ」ているというフレーズには一般的に違和感がともなう。
しかし、確かに私の沼津での、あるいはカッサンのコルシカでのノスタルジー体験は、まさしくノスタルジーが「開かれた」ものだからこそ生じたのではないか。私は沼津に「聖地巡礼」しに来た観光客であり、カッサンはコルシカに別荘を持っている客人である。どちらもその地に根を張った存在ではないが、確かにそこでノスタルジーを感じた。カッサンにいたってはそこが居場所 “Home” であるという明確な実感を持ちながら生活をしている。そこには確かに、”開かれたノスタルジー”のヒントがある。
ノスタルジーという現象は、人の居場所 “Home” と深い関係にある。もし、そのノスタルジーが開かれたものであるならば、人の居場所 “Home” というものもまた開かれた、拡張可能なものなのかもしれない。
□ ◆ □
─ 分断とは、思想の停滞
2022年、世界では新型コロナウィルスによる混乱が続いている。このコロナ禍の世界が後世からどのように語られるのかはまだ分からない。しかし、ウィルスそのものの脅威とは別に、人々が自分の「居場所」についてより一層、考えさせられた時代であったということは間違いないだろう。
感染対策の名のもとにさまざまな行動変容が起こる中で、「居場所」という観点を改めて提起したリモートワークの普及は注目に値する。これまで多くの人にとって、とりわけ日本において居場所といえば、主に家と会社との二つを指していた。しかし現在、オフィス空間はオンライン空間によって代替可能であり、精神的にも特別に重要な場所ではなくなりつつある。その一方で、家という場も、そこにずっといることで、むしろ気まずさや不安を感じてしまい、落ち着かなさをおぼえる人が続出した。すなわち、彼らにとって家 “House” も会社 “Company” も、実は居場所 “Home” ではなかったというわけだ。このことからも、居場所 “Home” はただ長い時間をそこで過ごせばできる、というほど単純なものではないことが分かる。
あるいは、家でも会社でもない第三の居場所、つまり「サードプレイス」という概念に可能性を見出す人もいるかもしれない。それはもちろん、大事な論点ではあるが、サードプレイスが実際に居場所 “Home” の代替になることは難しい。サードプレイスとは、家や会社での逃れられない人間関係の “重さ” を一時、忘れるための場であり、そこにおけるしがらみの無さや “軽さ” こそが魅力なのだ。だから、そのような “軽い” 場所は、あくまでも “重い” 場所があってはじめてその意味を持つものである。血縁に縛られるイエや、経済的安定性を供給する会社といった “重い” 場のつながりに代わって、趣味でゆるくつながっているような “軽い” 場を自分の居場所 “Home” として「格上げ」することは容易ではない。また、居場所とは、スイッチを切り替えするように器用に入れ替えられるようなものでもない。だからこそ、人々は居場所づくりというテーマに悩み続けるのだ。
それでは結局、人々はどのようにして居場所をつくればいいのだろうか。
人と人がつながることを、思想の世界では「連帯」と呼ぶ。これまで多くの思想家、運動家たちがこの「連帯」をキーワードに、この問題に向き合ってきた。この議論は、参考になる可能性がある一方で、大まかに二つの欠点がある。まず一つは「結局は愛や共感が大事である」、というような、お行儀のいい教養主義的な結論でお茶を濁してしまうものだ。たとえ非常に優れた分析が伴っていたとしても、このあまりにも「意識の高い」結論は空回りし、選民思想の亜種たちの「武器」を生み出すこととなった。たとえば、コロナ禍での「ステイホーム」をめぐる議論をSNSで検索すると、ステイホームできる「恵まれた人々」が、ステイホームできない人々を驚くほど意識の高い言葉でバッシングする、という場面がありふれている。そのような分断は、もはや日常茶飯事である。
もう一方は、主に思想の専門家たちによる、難解で神秘化された言葉を駆使しつつ、予言者的話法で連帯「論」を樹立しようとする試みだ。そのようなアクロバティックな言葉の空中戦は、専門家以外にとっての価値を生み出しているとは言い難い。結局のところ、それは一部の専門家や思想オタクたちの間でのみ流通するジャーゴンを生み出すばかりで、連帯を唱えながらも彼らの「ムラ」社会化を推し進めてしまうだけである。
コロナ禍をきっかけとして浮き彫りとなった、連帯の思想の停滞。それは停滞しているのみならず、逆に社会の分断をより一層進めてしまった。そう思うのは私の考え過ぎだろうか。
▷ ▼ ◁
─「錯覚」をたよりに “Home” を解明する
私は、この状況を踏まえて今一度、連帯の思想を根本から考え直す必要があると思っている。「人々はどうすれば連帯できるのか」という大命題よりも以前に、そもそも人々が連帯するということのメカニズム、人々の居場所の「構造」を解き明かす必要があるのではないか。そうすれば、これまでの連帯の思想の停滞を突破するためのヒントが得られるかもしれない。そして、そのヒントこそはノスタルジーという現象、より広く言えば「錯覚」にあると私は直感している。
ノスタルジーは、一種の錯覚に過ぎない。だがその錯覚は、観光客や客人のような「よそ者」にさえも強烈な帰属意識を与えてしまう。そうした錯覚こそが人々の集団を形作る。事実ではなく錯覚から引き起こされた意識が、人々の集団=居場所を開かれたものにする。そのような「錯覚」をめぐる試論を展開しようと思う。それは、「人の為すことは所詮、すべて錯覚に過ぎない」などといった安直なニヒリズムとはまったく別物の思想になるだろう。
この思想はおそらく、専門家やいわゆる思想オタクたちからすると飛躍のある、かなり「いい加減」なものになるだろう。しかし、意識だけが飛び抜けて高い人々のための「武器」を作るのでもなく、一部のシーンにしか通用しないジャーゴンの生産に耽溺するのでもない思想を展開しようとするならば、そのような「いい加減さ」は避けれないように思う。
そこで、これから本論を読む人たちには、次の一点を意識しながら読んで欲しい。それは、文章の内容を自分の心の中で再現できるかどうか、だ。論旨を追うだけではなく、その文章が示している状況を、自らが追体験できるかどうか考えてみて欲しいのだ。たとえば、「〇〇という状況になったときに、人は××という気持ちになる」という文章に出会った際、一旦立ち止まって心の中で、本当にそのような気持ちになるのか再現してみる。それは、読者にある程度の人生経験を要求するような読み方と言えるだろう。
知識や論理だけでは読めない。それは、現代では哲学というよりはむしろ、小説や映画のような文学の読み方に近いかもしれない。しかし、私は文章を大量の引用で固めたり、難解な用語を駆使するような現代哲学の論文的不自由さよりも、論理の飛躍を人生経験で読解していく文学のような自由さを追求していきたい。そもそも思想や批評を読むことは本来、そのようなものではないだろうか。そのような、私のささやかな意思を理解してくれる読者がひとりでもいてくれたら、書き手としてとても嬉しく思う。
それでは、「錯覚の哲学」をはじめよう。